
すべての生き物は”食”がつくる!
愛犬の食事が体の元気にどんな影響を与えるか、わかりやすくお話します!
中国伝統医学の知恵を取り入れた『愛犬のための薬膳ごはん』で、
老化をゆっくり進めて健康に一緒にいられる時間を増やしましょう!
日々のごはんに食材を少しトッピングするだけの、愛犬にぴったりの健康ごはんを作ってみませんか?
本記事では、
「薬膳とは!?」
「簡単というけれど難しいのでは…?」
というような、疑問や不安を分かりやすく解説していきます!
愛犬に健康的なごはんを食べてもらって、心を豊かにしましょう!
薬膳ごはんとは?中国伝統医学の考え方を取り入れた犬の食事
薬膳と聞くと「薬」をイメージしますが、実はそうではありません。
薬膳ごはんとは、日常的な食材を使って体のバランスを整える食事法です。
中国伝統医学の考え方に基づき、食材が持つ「性味」や「帰経」を活かして、愛犬の体調や季節に合ったごはんを作ります。
特別な薬や難しい調理法は必要なく、身近な材料で気軽に始められるのが魅力です!
薬膳の基本的な考え方
薬膳とは、中国伝統医学(以下、中医学)に基づき、健康維持や未病(病気を防ぐ)のために食材を活用する食事法です。
- 性味:食材の性質(冷やす、温めるなど)と味が持つ働きを活かす。
「性」は食材がもつ性能(ミントを食べると体が冷えるなど)
「味」は食材がもつ働き(大根を食べると胃もたれが解消するなど) - 帰経:食材が体内で特定の臓器に与える影響を考慮。
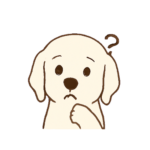 リバティー
リバティー薬膳と聞くとおくすりのイメージがあるけど、おくすりなの?



おくすりじゃないで!食材の力を活かして体のバランスを整えるねん。普段の食材で手軽に始められる!
中医学的に考える愛犬の健康と老化
中医学では体を「気、血、津液(体内の液体)」で捉え、バランスが大切。
- 老化のサイン:
- 季節の変わり目に体調を崩しやすい:暑い季節に元気がなくなる。
- 疲れやすくなる:少しの運動でも疲れたり、休憩を頻繁に取るようになる。
- 毛艶が悪くなる:毛がパサついたり、抜け毛が増える。
- 食欲の低下:食べる量が減ったり、好き嫌いが増える。
- 関節の痛みや動きの鈍さ:階段の上り下りを嫌がったり、歩き方がぎこちなくなる。
- 目や耳の衰え:目が白く濁る、聞こえにくそうな反応を見せる。
- 排泄のトラブル:尿の量や回数が変わる、排泄の失敗が増える。
上記は一例ですが、薬膳は普段のごはんに食材をトッピングして、この「老い」をゆっくり進行させ、健康維持に役立つことができます!
薬膳ごはんを取り入れるメリット
薬膳ご飯を取り入れると、以下のような良いことがあります!
愛犬に合った食事ができる
- 愛犬の体調や季節に応じて、最適な食材を選ぶことが可能。
特に冬の今であれば、旬で安いお野菜や果物を取り入れることができます。
わんちゃんが苦手なものは避けることもできるので、愛犬の好みに合わせて食材選びをすると良いでしょう。
- ドライフード、生食、加熱食など、どんな食事スタイルにも取り入れられる。
体調の変化に気づきやすくなる
薬膳を通じて愛犬の体調を細かく観察する習慣がつき、早めの対応が可能。
愛犬の体調や行動に注意を向けながら食事を準備することで、健康状態に気づきやすくなり、より深い絆を築くことができます。
健康的な長生きのために役立つ
- 薬膳は中医学に基づき、体のバランスを整える効果が期待できる。
- 未病先防(病気を未然に防ぐ)を目指す。
添加物の入っていないドライフードと薬膳を組み合わせることにより、より愛犬に良いごはんができあがります。
薬膳ごはんを取り入れるデメリット
反対に悪いこととして以下のようなことが挙げられます。
調理に手間がかかる
薬膳はその時の体調や季節に合った食事を作る必要があるため、食材選びや調理に時間や手間がかかることがあります。忙しい飼い主さんには負担に感じる場合もあります。
そのため、休日にまとめて作っておいて冷凍保管、解凍は常温またはぬるま湯で戻すなど工夫すると良いでしょう。
わんちゃんは猫舌のため、電子レンジなどで解凍するときは熱くなりすぎないよう、注意してください。
食費が高くなる場合がある
薬膳に使用する食材や調味料は、普段の食事よりも高価になることがあります。
特にオーガニックや質の高い食材を選ぶ場合は費用がかさむ可能性があります。
薬膳ごはんおすすめ食材
冬におすすめの食材と効能
- 山芋:全ライフステージで使用可能。必ず加熱して提供。
- 白きくらげ:陰を補う食材。美容効果も期待される。乾燥時は粉にするのもOK。
- りんご:肺を潤し、消化を助ける。生または加熱で。
季節に応じた薬膳スープの例
- 夏(陰を補う):白きくらげ、りんご、鶏肉。
- 冬(体を温める):山芋、鹿肉、ショウガ少量。
ショウガはチューブではなく、生のものをすり下ろして与えましょう。
冬の水分不足に薬膳ごはんを取り入れよう
冬は寒さの影響で、多くのわんちゃんが水を飲む量が減りがちです。体内の水分が不足すると、健康を損なう原因にもなります。そんな時におすすめなのが、薬膳スープを取り入れた水分補給です!
薬膳スープで手軽に水分補給
1. 水分摂取量の目安
わんちゃんが1日に必要な水分量は、以下の計算式で求められます
体重(kg) × 50~60ml
例:体重30kgのわんちゃんの場合、1日で約1,500mlの水分が必要です。
2. 冬に水を飲まないときの工夫
寒い時期には水を飲む量が減るわんちゃんも多いですが、以下の工夫で水分摂取量を増やせます
- 香り付けをする:ヤギミルクやヨーグルトやボーンブロス(骨のスープ)を少量混ぜて、飲みやすくする。
- 少量ずつ頻繁に与える:体に吸収されるお水の量は決まっているので、一度に多く飲ませるのではなく、少量ずつ何回かに分けて与えると良いです。
- 人肌くらいの暖かいお水を与える:その都度器にお水を注がないといけないですが、飲んでくれるのであれば暖かいお水を与えるのはおすすめです。
フードのふやかし方で胃の負担を軽減
ドライフードのふやかし方
ぬるま湯でしっかりふやかしてから与えることで、胃の中でフードが膨らむのを防ぎ、胃の負担を軽減できます。熱すぎるお湯でふやかすと、ドライフードの栄養素が壊れてしまいますので、36℃〜38℃でふやかすと良いでしょう。
薬膳スープでふやかすと、さらに健康効果が期待できます!
薬膳スープの作り方
- 食材はできるだけ細かく刻むかすりおろしておく。
- 1つの鍋で食材をじっくり煮込み、スープを作ります。
- スープでフードをふやかし、具材は細かく混ぜ込むことでわんちゃんが食べやすくなります。
- 味付けは調味料ではなく、食材そのものの「うまみ」を利用する。
注意点
- 食べた後、未消化の便が見られた場合、その食材は避けましょう。
- 消化しにくい食材(ニンジン、大根、じゃがいもなど)は、すりおろしや加熱調理で消化しやすくしてから与えることがポイントです。
リバティーの薬膳ごはんの体験談
愛犬リバティーは体重が30kgで、計算すると1日に約1,500mlの水分が必要ですが、冬になると飲む量がぐっと減ります。
そこで、薬膳スープを使ったごはんを取り入れてみたところ、リバティーも喜んで食べるようになり、水分もしっかり補給できました!
例えば、ボーンブロススープは、体を潤しながら健康をサポートしてくれるのでおすすめです。冬場の水分補給の悩みを解決しながら、美味しく体を整えられるのが薬膳ごはんの魅力です!
薬膳ごはんを始める際の注意点
動物種や個体差を考慮する
一部の食材は犬にとって有害(例:玉ねぎ、ニンニク)です。与えては行けない食材は事前に知っておきましょう。
食物アレルギー反応があることもあるので、アレルギーには注意して食材を選びましょう。
獣医師に相談しながら進めるのが安心です。
無理なく始める工夫
毎日のごはんに簡単に食材を加えるだけでも効果が期待できます。手軽な食材(山芋、りんごなど)からスタート!
まとめ:愛犬の健康のために薬膳ごはんを取り入れよう
薬膳は「食べることで健康を守る」考え方に基づいており、未病や老化のケアに最適。老化をゆっくり進めて、わんちゃんと健康に居られる時間を増やしましょう!
コメント